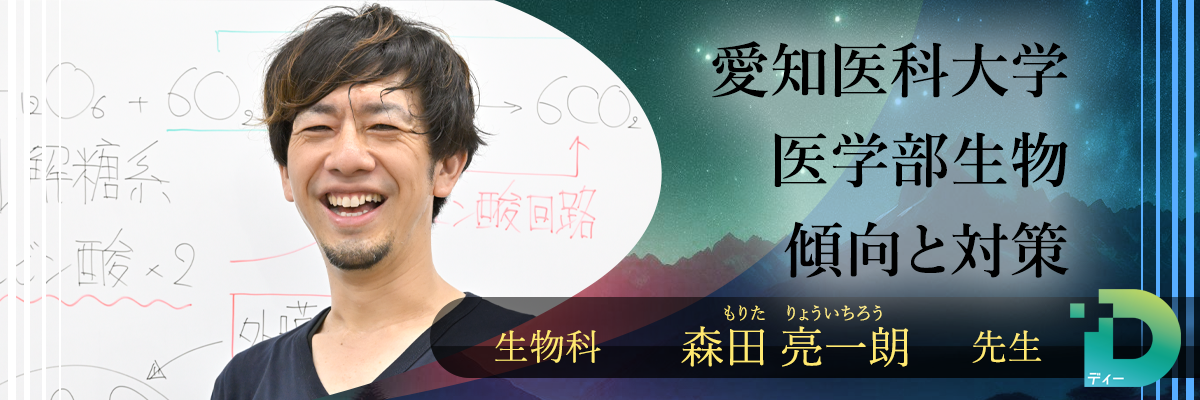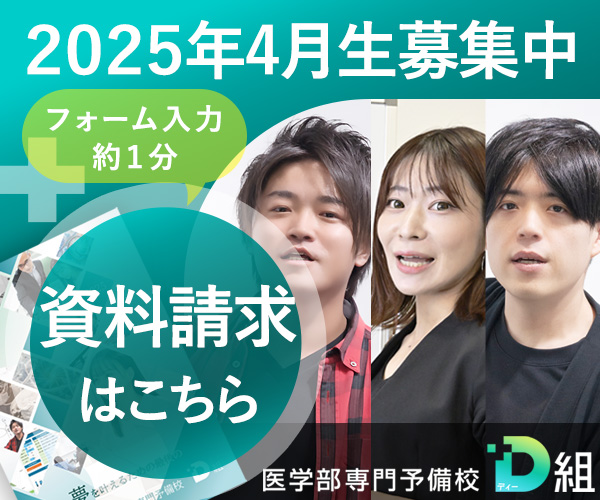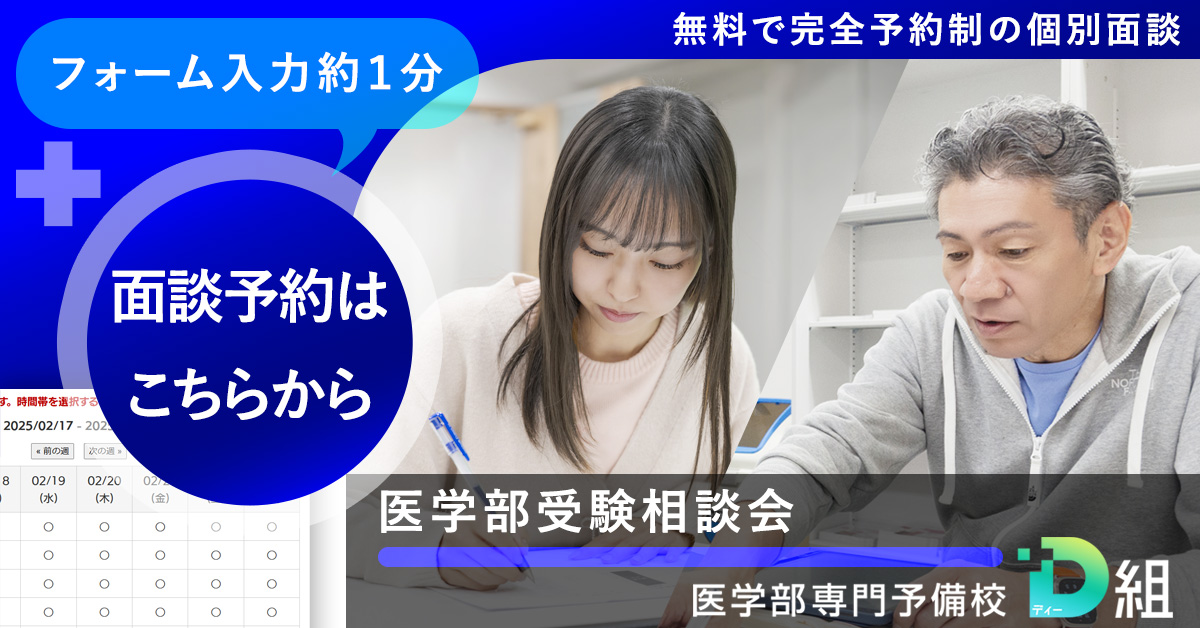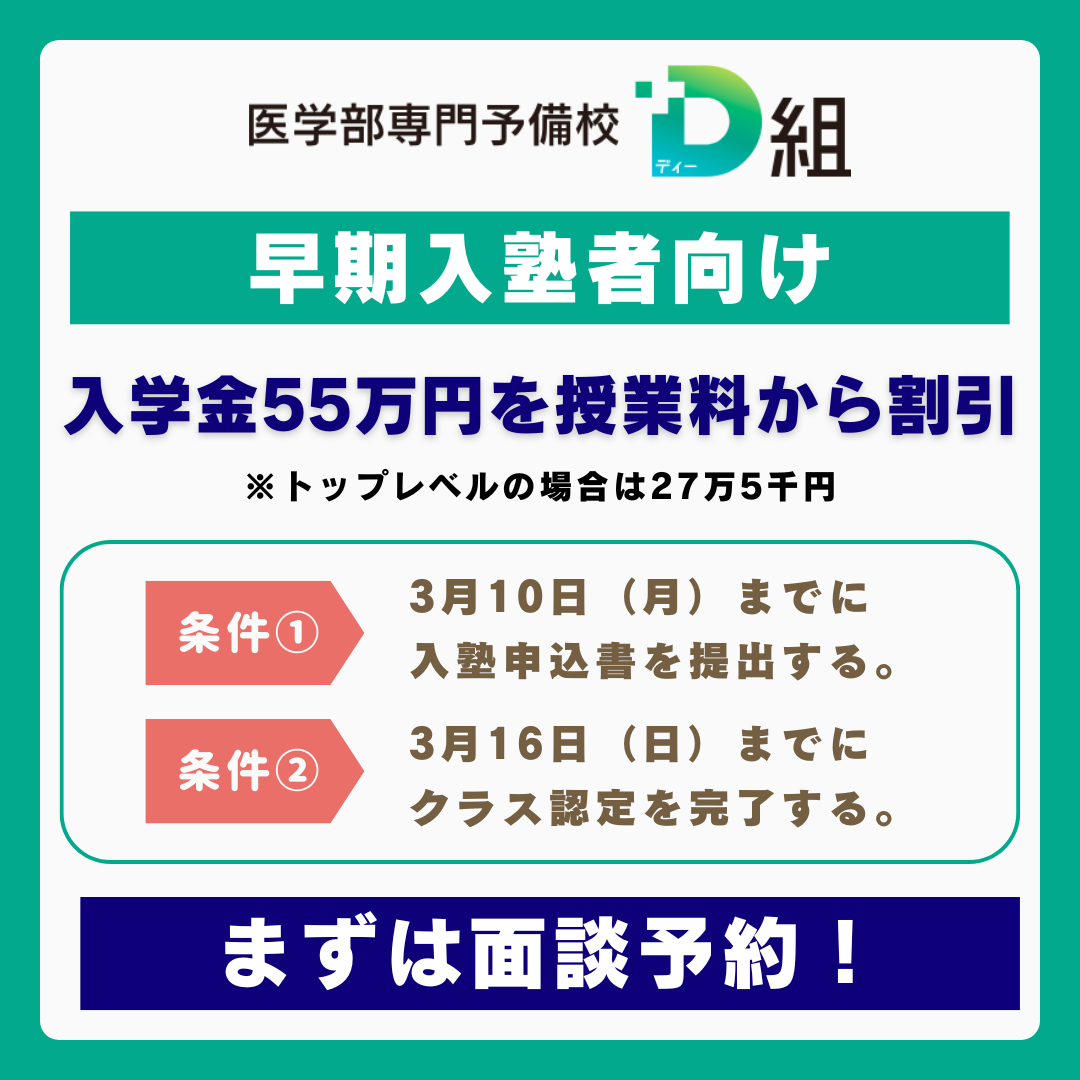今月は医学部専門予備校D組生物科講師の森田亮一朗先生に愛知医科大学生物の入試対策をお聞きしました。
「遺伝情報」「体内環境」「動物の反応」の3分野が頻出!
森田亮一朗先生よろしくお願いいたします。早速ですが近年の愛知医科大学の生物には特別な傾向はありますか。
近年の愛知医科大の出題テーマは以下の通りです。
| 年度 | 大問 | 出題テーマ | 分野 |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ⅰ | 遺伝子導入 | 遺伝情報 |
| Ⅱ | 被子植物の配偶子形成と受精 | 植物の反応 | |
| Ⅲ | 興奮の伝導と伝達 | 動物の反応 | |
| 2024 | Ⅰ | 自然選択,分子進化 | 進化・系統,遺伝情報 |
| Ⅱ | マウスの嗅覚と忌避行動 | 動物の反応 | |
| Ⅲ | 酸化ストレスに対する遺伝子応答 | 遺伝情報,体内環境 | |
| 2023 | Ⅰ | 森林の階層構造,生命表,絶滅の要因 | 生態 |
| Ⅱ | 遺伝子突然変異,遺伝暗号の解読 | 遺伝情報 | |
| Ⅲ | 脱水素酵素の実験,酸素解離曲線 | 代謝,体内環境 |
2025年度の入試問題を踏まえて愛知医科大学生物の傾向を分析すると
- 「遺伝情報」「体内環境」「動物の反応」からの出題が頻出である。
- 論述問題が多く課される(今年度は7問)。
- 今年度は出題されなかったが,計算問題と描図問題が課されることが多い。
(2024年度)計算問題:分子時計 / 描図問題:分子系統樹の作成
(2023年度)計算問題:生命表の完成 / 描図問題:陽葉と陰葉の光―光合成曲線
という特徴が見られます。また,入試全体のトレンドですが分野横断の出題も近年多くみられます。
頻出分野の対策は当然! 手薄な分野があると合格が遠のいてしまう!
森田亮一朗先生としては,その傾向にはどういった大学の意図が現れていると想像されますか。

「遺伝情報」「動物の反応」「体内環境」の3分野は、基礎医学と深く関わっているため、医師を目指す受験生にとって特に重要であり、積極的に学習することが推奨されます。
しかしながら、愛知医科大学が求めているのは、あくまで高校生物の範囲であり、いわゆる医系生物のような高度な内容ではありません。高校の教科書に準拠した知識を正確に理解し、定着させることが最も重要です。
高校生物をしっかりと学習することが求められる背景には、毎年3大問のうち1問が、上記3分野以外――たとえば「生物の多様性」「生態」「植物の反応」などの分野――から出題されているという事実があります。
こうした分野を疎かにした結果、たまたま出題された際に大幅な失点をしてしまうと、合格から大きく遠ざかってしまいます。
「偏差値が高い難問演習の必要があり」ではない!
現在,まだ合格水準に足りていない受験生が愛知医科大学医学部の合格水準に達するための努力としてはどういったものが考えられますか。
医学部進学を目指す受験生の中には、「私立医学部は偏差値が高いので、旧帝大や早慶レベルの問題で鍛えるべきだ」と考える方が少なくありません。この考え方が全くの誤りとは言えませんが、果たしてそれが本当に愛知医科大学の合格に必要な学習なのでしょうか。
愛知医科大学の入試では、教科書レベルを中心とした標準的な問題が数多く出題されます。そのため、こうした問題を確実に正解できるように訓練しておくことが合格への第一歩です。基礎事項を徹底的に押さえ、ケアレスミスを防ぐ力を養うことが、最も安定して得点を重ねる近道となります。
一方で、愛知医科大学では50~100字程度の記述・論述問題が毎年出題されることも特徴のひとつです。記述問題の内容は、図やデータをもとに論理的に説明する力を求めるものが多く、単なる知識の暗記だけでは対応できません。日頃から教科書の記述を自分の言葉で説明する練習や、典型的な記述問題の解答例を模写・添削しながら記述力を高めておくことが重要です。
まずは「リードα」「セミナー」「ニューグローバル」「センサー」などの教科書傍用問題集をしっかりと仕上げ、標準問題を完璧に解けるようにすること。さらに記述問題の対策を通じて、表現力と論理的思考力を養っていくことが、愛知医科大学の生物で得点するための王道です。
愛知医科大学の入試は共通テストの翌週! 対策は早い時期から! !
これまで愛知医科大学医学部に合格してきた受験生にはどういった特徴がありましたか。

愛知医科大学の入試において、最も確実な対策は何か。それは言うまでもなく「過去問演習」です。愛知医大の出題形式には特徴があり、記述問題の頻度や標準的な知識問題の比重は、他の私立医学部と比べてもやや独特です。だからこそ、過去問を通して傾向に早く慣れておくことが極めて重要になります。
特に国公立大学との併願を考えている受験生は注意が必要です。12月以降は共通テスト対策に時間を割かざるを得ないため、私立医学部の過去問対策に十分な時間を取れなくなるのが実情です。愛知医科大学は2026年度も共通テストの翌週に入試が行われるため、12月の段階で完成度を高めておく必要があります。後回しにせず、9月・10月には過去問演習をスタートさせましょう。
また、医学部合格者に共通するのは「学習への柔軟さ」と「目の前の課題への真摯な取り組み」です。奇抜な方法を求めるのではなく、先輩の成功事例や信頼できる指導のもとで、確実に基礎を積み上げていく姿勢が不可欠です。
加えて、モチベーションを高く保つためには、「興味を持てる分野をひとつでも見つけること」が大きな武器になります。得意な分野があると、それが生物全体の得点力を底上げし、他のテーマにも自然と関心が広がっていくものです。
最終的に合否を分けるのは、戦略的に「いつ・何を・どのように学ぶか」です。愛知医科大学の入試日程を踏まえた学習スケジュールを早期に立て、過去問と記述対策を軸にした実践的な演習を進めていきましょう。
ペース配分を間違わないように! 論述問題は慌てて書くと失点の可能性大!
愛知医科大学医学部の入試当日に気を付けてほしい点はありますか。
愛知医科大学の理科試験は、2科目合わせて100分という形式で実施されます。この時間設定は、一見すると余裕があるように感じるかもしれませんが、決して油断はできません。特に生物では、記述・論述問題の比率が高いため、解答に時間がかかることが多く、ペース配分を誤ると後半の設問で時間切れになるリスクがあります。
理科2科目で100分ということは、1科目あたり単純計算で50分ですが、問題の構成や個人の得意不得意によって多少の前後は想定しておくべきです。時間がかかる記述問題が多い生物を後に回すと、焦りながら論述を書くことになり、ミスや論理の飛躍が起こりやすくなります。一方で、生物を先に解きすぎて物理や化学にかける時間が足りなくなるのも避けたいところです。
したがって、事前に「生物〇分、化学〇分」のように自分なりの配分プランを立てておくことが非常に大切です。過去問演習を通して、実際に時間を計りながら練習し、「この時間内で記述も含めて仕上げられる」という実感をもって本番に臨めるようにしておきましょう。
また、論述では、完璧な文章を1回で書き上げようとすると時間がかかりすぎてしまいます。まずは要点をメモにまとめてから、それをもとに簡潔で論理的な文を構成するというステップを身につけておくと、安定して得点できるようになります。
試験本番では、内容以前に「時間配分の戦略」が得点を左右します。平常心で実力を出し切るためにも、当日のシミュレーションを十分に行い、戦略的に試験に臨んでください。
いま、この瞬間から始めよう! 一愛知医科大学を本気で目指すあなたへ
これから受験勉強を本格的に始める受験生に熱いメッセージをお願いします。
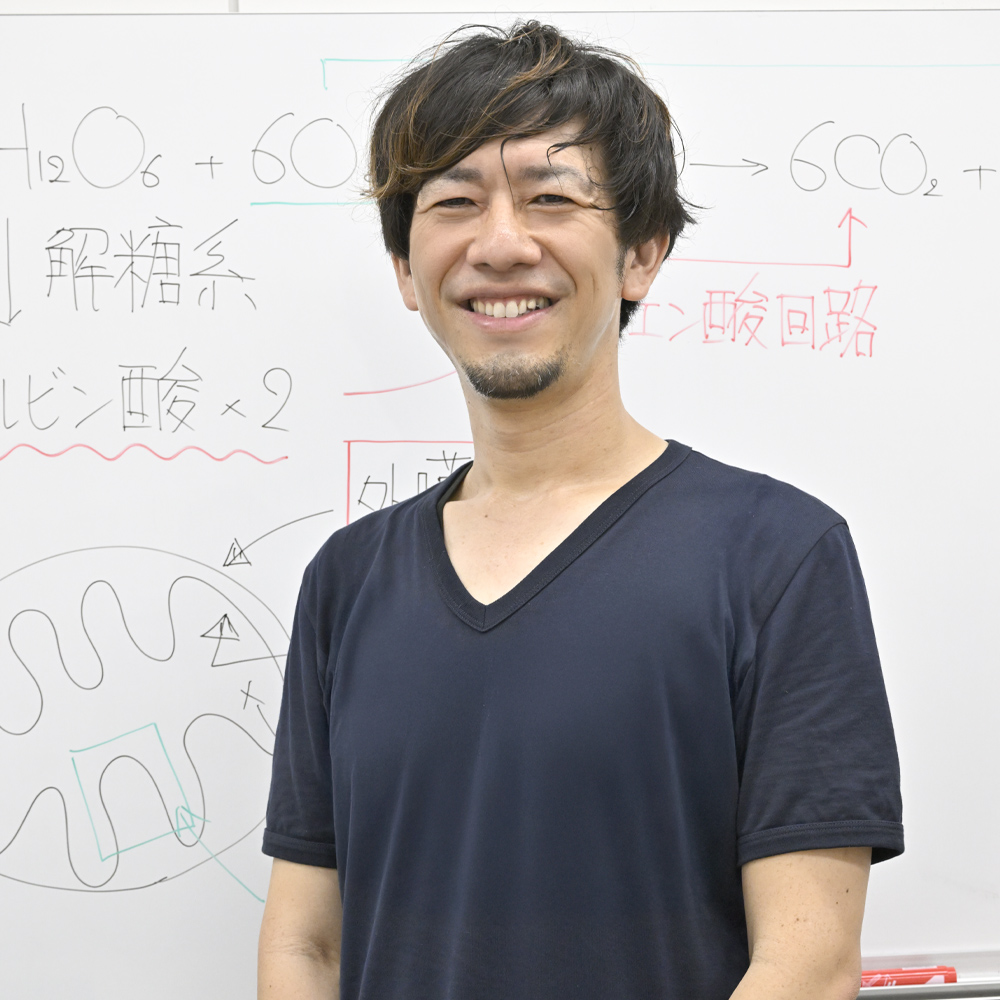
医学部を目指すという決意は、簡単なものではありません。誰よりも高い目標に挑み、誰よりも長く、深く、考え抜く日々が待っています。けれども、その先には、誰よりも大きな達成感と、未来への扉があります。
愛知医科大学を本気で目指すなら、「今」が勝負です。
愛知医科大学の入試は、共通テストのわずか数日後に始まります。つまり、ほとんどの受験生が「切り替え」に苦しんでいるそのときに、すでに準備を終えている者が大きく前に出るのです。過去問に早めに取り組み、標準問題を確実に解ける力をつけ、論述対策で自分の言葉で説明する練習を積んでおけば、本番で慌てることはありません。
理科2科目・100分。時間との戦いの中で、冷静に、戦略的に動けるかどうかが合否を分けます。だからこそ、普段の演習から本番を意識し、「どうすれば自分の力を出し切れるか」を常に考えてください。
そして、生物学を最高に楽しんでください!生物に夢中になれる時間が、受験勉強を支える本当のエネルギーになります。迷うときも、つらいときもあるでしょう。でも、努力を重ねるあなたには、その努力にふさわしい未来が待っていますよ。
私は細見言者です!
最後に森田亮一朗先生の好きな音楽を教えてください。
ELLEGARDENというバンドが好きです,むしろ愛しています。
つらい時期に聞いて支えられた音楽というのは,いつになっても心の支えになりますよね。
なるほど,森田亮一朗先生ありがとうございました。引き続きD組の医学部受験生たちにも熱意あるご指導をよろしくお願いいたします。
医学部専門予備校D組では現在の成績に関係なく10人程度の少人数クラスで森田亮一朗先生の生物の対面講義を受けることができます。少人数制だからこそ可能なきめ細やかな指導と、質疑応答の時間を豊富に設けることで生徒一人ひとりの理解度を深め、着実に実力アップを目指します。さらに、アットホームな雰囲気の中で周りの生徒と切磋琢磨しながら学ぶことができるのもD組の魅力です。