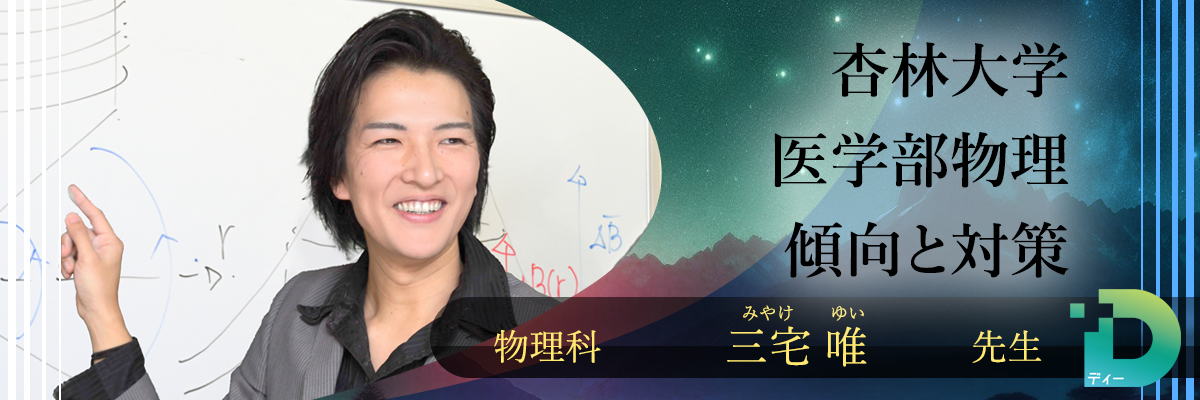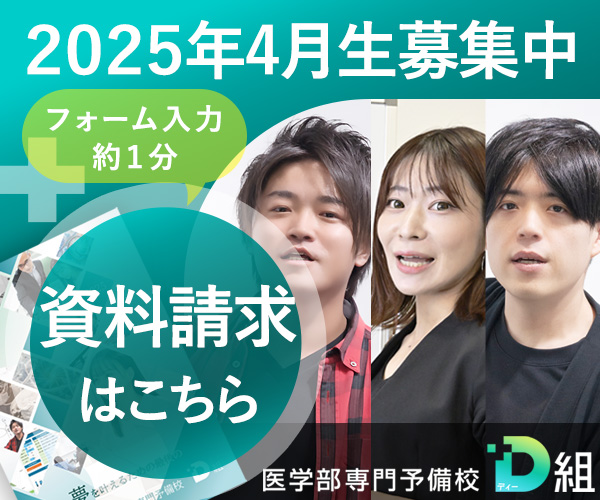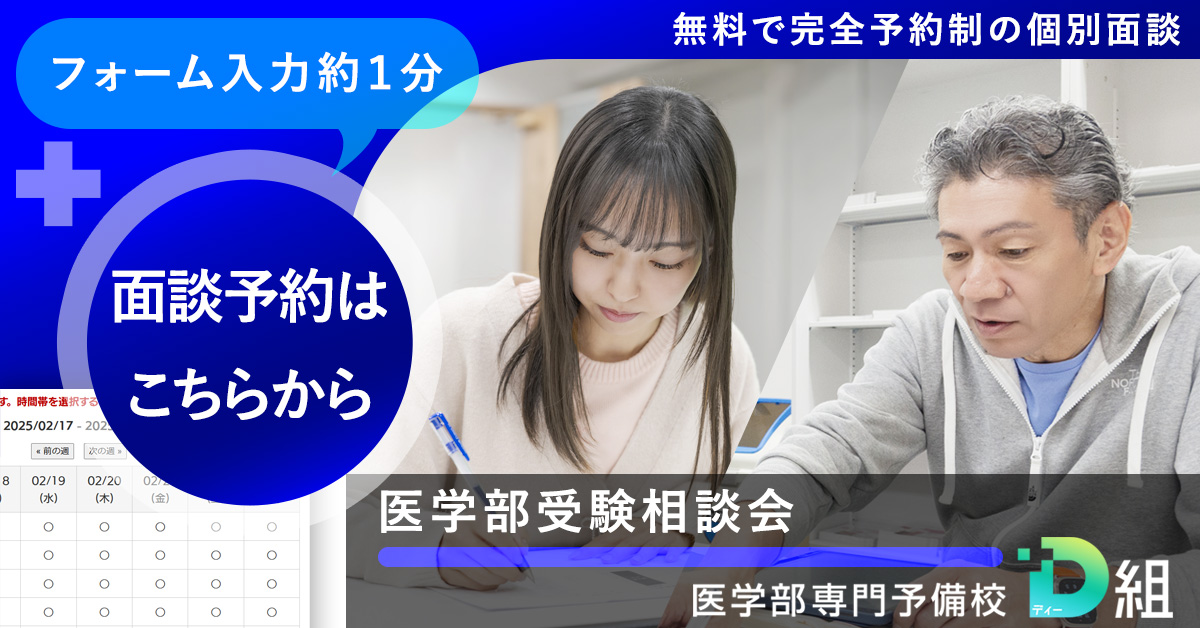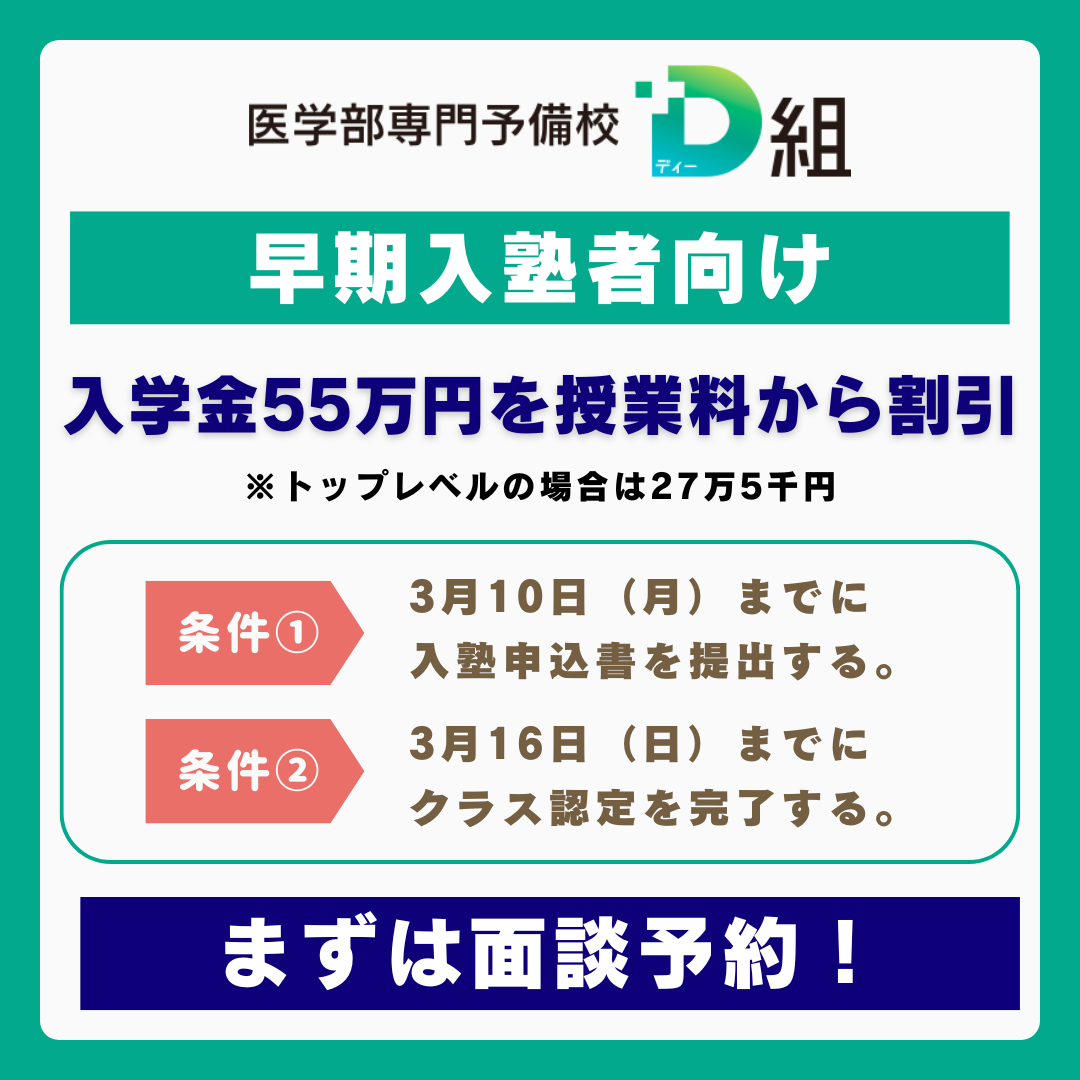杏林大学医学部物理(2025年度/一般)-入試情報
出題形式
選択肢
試験時間
50分(理科2科目100分)
難度(5段階)
3.1(標準)
分量(必要時間)
58分
合格に要する正答率予想
66%
大問数
3問
出題内容
第1問:原子核,第2問:水平面上のばねでつながれた2物体の運動,第3問:ダイオードを含む回路・半導体
求められているもの
普段の研究で得た結果を一足飛びに適用しなければ時間的に厳しい。第1問の計算問題では,計算結果が簡単になるように調整されておらず,やや煩雑な数値計算をミスなくこなす能力が問われている。今年の分量はさほどでもないが例年分量が多いため,優先して解く問題を見極める力が必要である。また他ではあまり見ないような,問い方が独特な問題もある。このような出題傾向から,計算力・応用力・見極力をバランスよく兼ね備えた学生が求められていると考えられる。
杏林大学医学部物理(2024年度/一般)-入試情報
出題形式
選択肢
試験時間
50分(理科2科目100分)
難度(5段階)
3.3(標準)
分量(必要時間)
65分
合格に要する正答率予想
72%
大問数
4問
出題内容
第1問:小問集合,第2問:小問集合,第3問:水平面上における衝突,第4問:帯電した正方形物体が磁場から受ける力
求められているもの
4問中2問を占める小問集合では,数値を解答する問題が大半を占める。計算結果が簡単になるように調整されておらず,やや煩雑な数値計算をミスなくこなす能力が問われている。テーマ性のある残りの2問では,普段の研究で得た結果を一足飛びに適用しなければ時間的に厳しい。総じて典型的問題が多い反面,分量が多いため解ける問題を見極める力が必須である。このような出題傾向から,計算力・応用力・見極力をバランスよく兼ね備えた学生が求められていると考えられる。
※難度、分量、合格正答率は講師コメント・編集部推定。
今月は医学部専門予備校D組物理科講師の三宅 唯先生に杏林大学物理の入試対策をお聞きしました。
解法が思いつかない時点で門前払い
三宅 唯先生よろしくお願いいたします。さっそくですが,杏林大学の物理にはどのような特徴があるとお考えですか。

こちらこそ,よろしくお願いいたします。杏林大学医学部の物理ですね。結論から言えば「典型問題を正確に速やかに解けるか」が問われる試験だと感じています。
2024年度も2025年度も,出題されているすべての問題は受験生が一度は目にしたことのあるテーマばかりです。数値計算や穴埋めなどの解答様式によって解きづらさを感じるのは仕方ないですが,「根本的に問題の言っていることがわからない」とか「解法が思いつかない」とか,そういった解きづらさを感じる問題が1問でもあるならば,純粋に勉強不足です。その時点で杏林大学医学部の受験資格はありません。予選敗退どころか門前払いです。いや,実際のところはそんなことはないと思いますが,それぐらいに厳しくとらえておいた方がいいということです。分野にも特に偏りはなく,「力学,電磁気,波動,熱力学,原子物理」の全分野からまんべんなく出題されており,難度にも偏りはなく,特に奇をてらったトリッキーな設問というのは見受けられません。
ただし,油断は禁物です。いずれの年度も,桁の多い数値など計算処理や情報整理の煩雑さという「手強さ」はそれなりに盛り込まれていて,「ただの典型問題」として安易に分類することはできません。
なお,数年度にわたって統計すると全分野からまんべんなく出題されているのですが,制限時間が理科2科100分と短いためか,単年度では全分野網羅を意識せずコンパクトに出題していることも杏林大学の特徴の一つです。
煩雑な数値計算はおそらくアドミッションポリシー
なるほど。では「処理力」が重要ということでしょうか。

はい,そのとおりです。杏林大学の数値計算問題には「除算において計算が簡単になるように数値を与えてくれる」などの配慮はありません。多くの大学の試験で求められる物理の能力とは異なる能力を求めているんだろうなと感じます。
「物理講師の私」としてはなるべく計算が簡単になるように数値を与え,有効数字一桁程度で出題してほしいなと思うところもあります。扱う現象にもよりますが,高校物理水準のモデル化や法則の精度はあまり高くありません。このため,入試物理で高い精度の数値計算を出題することには,個人的にはあまり意味を感じないのです。もっと良い精度で得られるモデルを大学で学習してから,コンピュータを使ってシミュレーションする方が実用的だな,と感じます。高校物理だけでも考えられる現象はそれなりにありますが,未熟さも併せ持っており,高校物理はまだまだおままごとの域をでない物理です。それでも多くの方々にとって馴染みのない考察に溢れており,法則を適用できるようにするだけでも精一杯です。私としては,数値計算は出題するにせよ,お手柔らかにお願いしたいな,と思います。
もちろん計算が煩雑な数値計算を出すことが悪だとは言っていません。それは物理の問題である前に医学部の入試問題であるからです。ですから絶対に勘違いしないでほしいです。これは「物理を物理らしく出題して受験生の物理の能力だけを見るテスト」ではありません。医師としての資質を測るために工夫された結果として完成した「物理の分野からなる医学部入試問題」です。医学部入試は医師への就職試験を主眼に作成されているのですから,他学部に比べて異なる特徴を有するのは当たり前のことです。杏林大学は煩雑な数値計算を乗り越える注意力の高い学生を求めており,それは杏林大学のアドミッションポリシーに準じた出題傾向と考えてよいでしょう。
このような問題で合格ラインを越えるには,「時間内に確実に解けるものを見極める能力(見極力)」と「丁寧に検証しながら解き進める堅実さ」が同時に必要です。あらゆる問題に真っ向勝負で立ち向かう,というよりは,攻めるべきところと引くべきところのメリハリが大切なのです。見極力も堅実さも豊富な問題演習経験に裏打ちされるものです。充実した問題演習をしましょう。
ミスに厳しい姿勢を
では,杏林大学が求めている受験生像というのはどのようなものでしょうか。
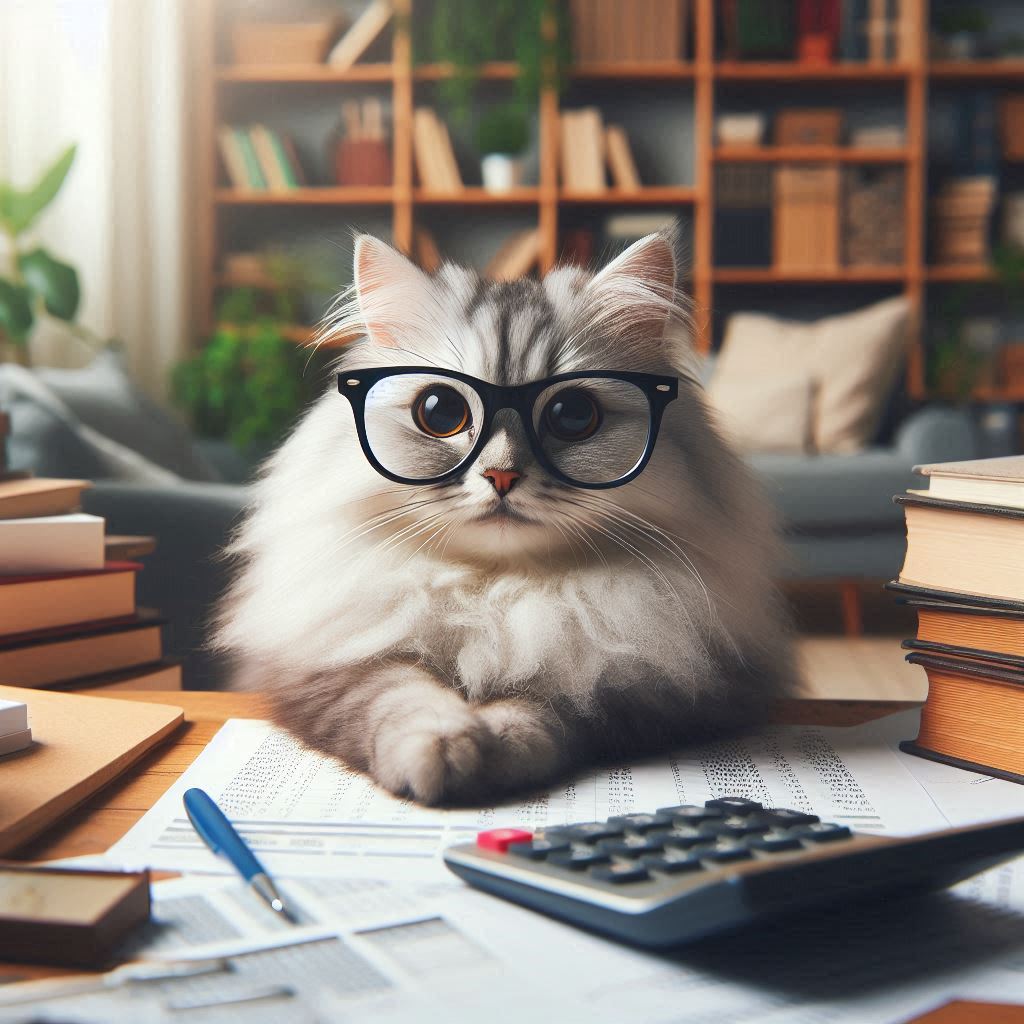
杏林大学が求めているのは「計算力・応用力・見極力をバランスよく兼ね備えた受験生」だと考えます。この三つの力は,いずれか一つだけでもバランスを欠けば点数が伸びません。
たとえば計算力に自信があっても,初見の設定で固まってしまって手が止まるようでは合格圏には届きませんし,応用力に優れていても途中式でミスが続けば得点になりません。杏林大学では初見の設定の問題を見つけることが難しいくらいに勉強しておくことが最低限なので,計算力も応用力も圧倒的に充実した問題演習でねじ伏せてください。また,分量が多いため「時間を使う問題を捨てる判断」すなわち見極力を要しますがこれも問題演習でねじ伏せることができます。
加えていうなれば,面倒な数値計算を多く出題するのは,おそらく,単純な作業でミスが多い人間を入学させないためです。試験時間が少ないため,敬遠する受験生も多いと思いますが,「数値計算問題だけ無解答」は不安です。この種の問題は医師への適性という意味を持った問題ですから,多少は取り組んでおいたほうが無難かと思います。
総じて杏林大学で求められているのは,試験日までの堅実な準備です。外科手術と同様に,試験は「出たとこ勝負でその場で試行錯誤するもの」ではありません。「ちょっとこれ,よくわからないけど,とりあえず切ってみるか…あ,いっぱい血が出てきた!ミスったわ,ドンマイ!」じゃありません。試験までにたくさん試行錯誤して,たくさん失敗し,絶対に失敗しない判断基準を養っておくのです。試験日その日までに考えうるすべてを用意しておくのです。考えが足りないことは許されません。日頃から自分のミスに厳しい姿勢でいてください。
小間集合に注意する
2024年度と2025年度で,何か大きな違いはありましたか。
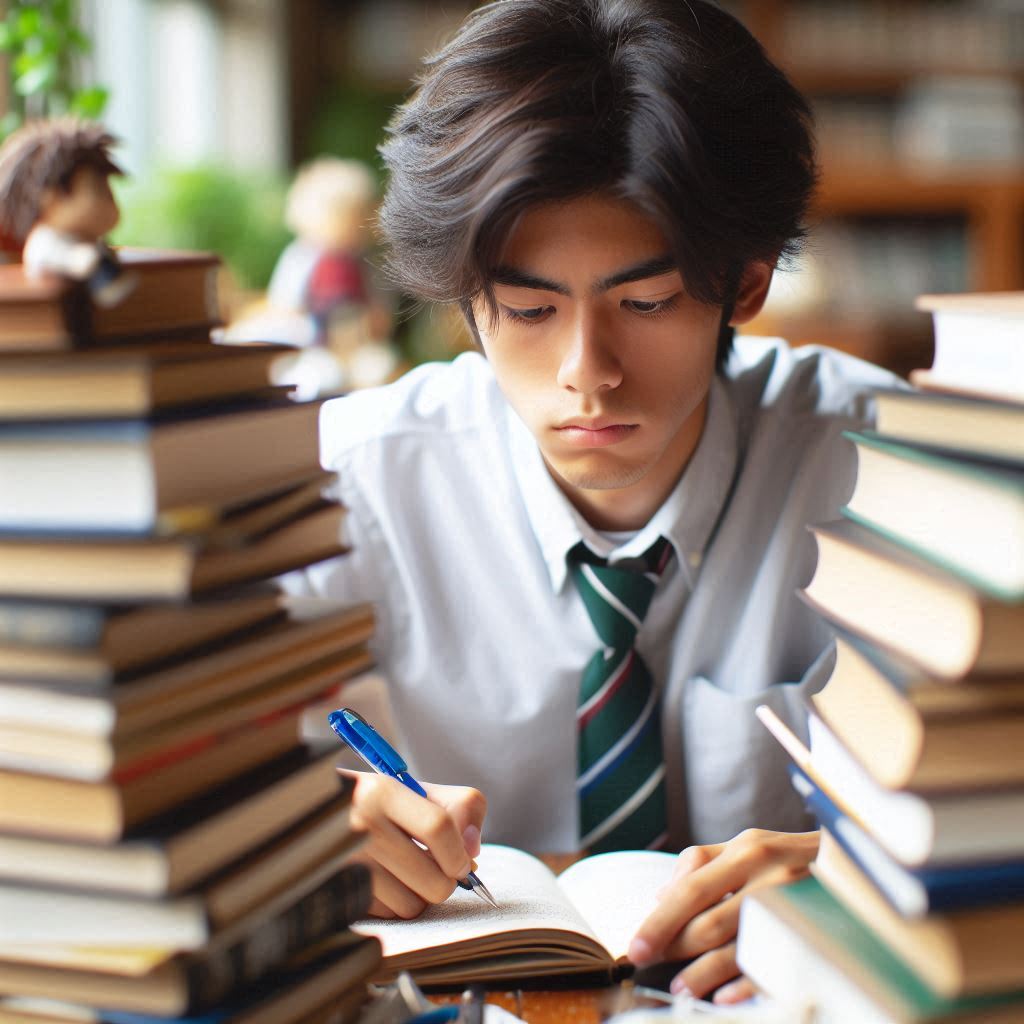
大きく異なるのは「小問集合」の有無です。2024年度は4問構成でそのうち2問が小問集合でしたが,2025年度では3問構成に変更され,小問集合が廃止されました。2024年度以前も極めて長い間,構成変更はありませんでしたから異例のことです。しかし,大問数は減少しても解答に時間がかかる問題が多く,実質的には分量は大きく変わっていません。かつ,難度もほとんど変化がありません。よって,次年度以降も小問集合がなく,3問構成を維持し続けるかどうかは全く判断できません。このため,小問集合の対策もしておくとよいでしょう。
小問集合は短い問題文で単発の知識を問う小問の集合です。多くの場合,各小問のテーマはすべて独立であり,出題分野を広げる目的で導入されています。浅く広くといったところでしょうか。
しかし小問集合は決して易しいものではありません。問題文が短くモデルの説明が薄い問題も散見されます。モデルの説明が足りないと,同じような問題を解いたことがない受験生は題意を把握することができず,解答不能となることもあります。これも豊富な問題演習経験によってねじ伏せましょう。しかし,経験によって判断して大きな間違いをおかすこともあります。過信せず問題文を注意深く読みましょう。また,各小問でテーマが異なるので頭の切り替えが得意な受験生に有利です。1つのことをしっかり考えることが好きな受験生には不利に働くこともあります。自分のタイプをしっかり見極めたうえで対応を考えましょう。
対策は筋トレ的な学習
杏林大学医学部にはどのような学習法が有効でしょうか。

第一に,最低限の基礎理論の習得です。学校や塾・予備校の講義をしっかり受けてください。杏林大学の本試では「現象の本質に迫る」というような基礎的な問題はあまり見ないので,最低限で大丈夫です。復習に復習を重ねて「理論講義を完全に再現することができる」という水準までは必要ないです。しかし,「杏林大学だけを受けるわけではない」という方は他の受験大学での必要性に応じて復習を重ねてください。
第二に,大量の問題演習です。ここに最大限の時間をかけてください。標準的な市販の問題集で合計1000問以上を完璧に解けるようになるまでやり続けてください。ここに基礎理論の習得のために解いた問題数と過去問と模試の問題数は含みません。
第三に,過去問演習です。遡れるだけ遡って演習しましょう。このときに見たことのないパターンの問題でも「よくわからないけど答えは出る」というレベルに達していれば成功です。過去問演習を続けてください。そうでなければ第一,第二に不足している部分があります。自分を見つめ直しましょう。
体当たりの学習を
逆に,ありがちな誤った学習法はありますか。
細かいことにつまずいて先に進まない学習です。とりあえず無理やり覚えて先に進んでしまおうと解決を先送りする決断も大切です。後で考えるとスッキリわかることも多いからです。原理からの法則導出なども後回しで大丈夫です。杏林大学ではあまり出題されない傾向にあるからです。実用的に物理法則を適用する方法を学びましょう。
成功にこだわる学習も危険です。たくさん失敗して体当たりで学びましょう。考えている時間より手を動かしている時間を増やしましょう。
力はフォース
最後に,杏林大学医学部を志望する受験生へのメッセージをお願いします。
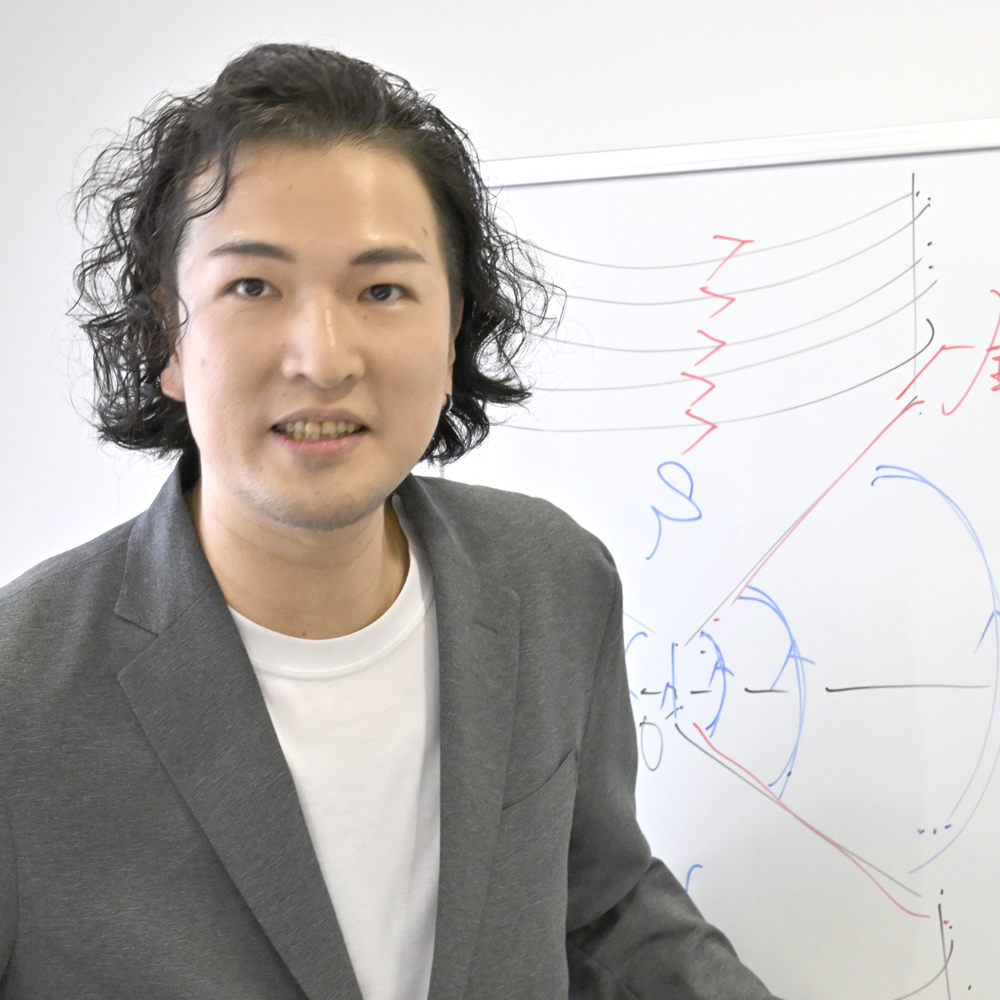
杏林大学は,決して変わった問題を出すわけではありません。しかし,まっすぐな分だけ腕力が必要です。試験は真正面から腕力でねじ伏せ続ける50分です。
この戦いに勝つには,やはり愚直に演習を重ね,計算処理の力を養い,状況を的確に読み取る練習を積むしかありません。受験は孤独な戦いに思えるかもしれませんが,物理はあなたが世界をねじ伏せるための力になります。力こそパワーです。目の前の現象を片っ端からねじ伏せていける日がきっと来ます。
その日を信じて,どうか,今日も筋トレに励んでください。応援しています。
私としては,力はフォースだと思います。
なるほど,三宅 唯先生ありがとうございました。引き続きD組の医学部受験生たちにも熱意あるご指導をよろしくお願いいたします。
医学部専門予備校D組では現在の成績に関係なく10人程度の少人数クラスで三宅 唯先生の物理の対面講義を受けることができます。少人数制だからこそ可能なきめ細やかな指導と、質疑応答の時間を豊富に設けることで生徒一人ひとりの理解度を深め、着実に実力アップを目指します。さらに、アットホームな雰囲気の中で周りの生徒と切磋琢磨しながら学ぶことができるのもD組の魅力です。