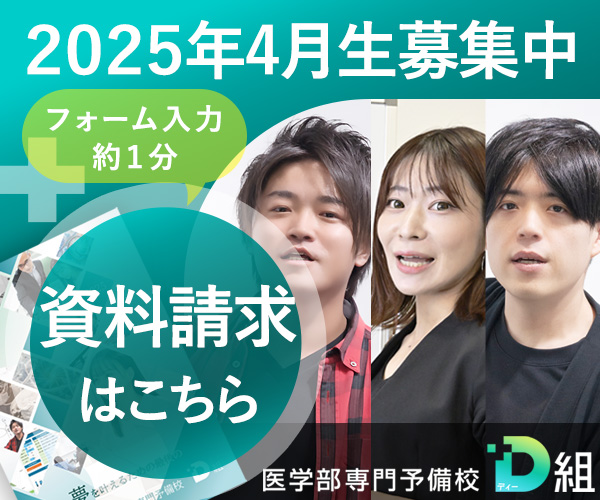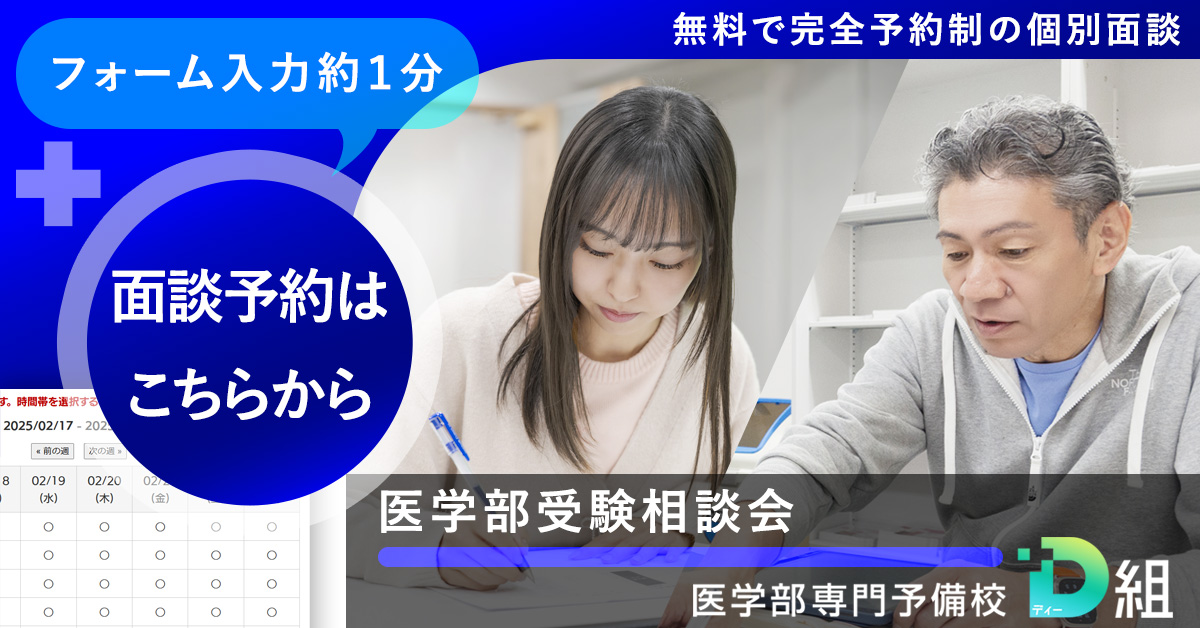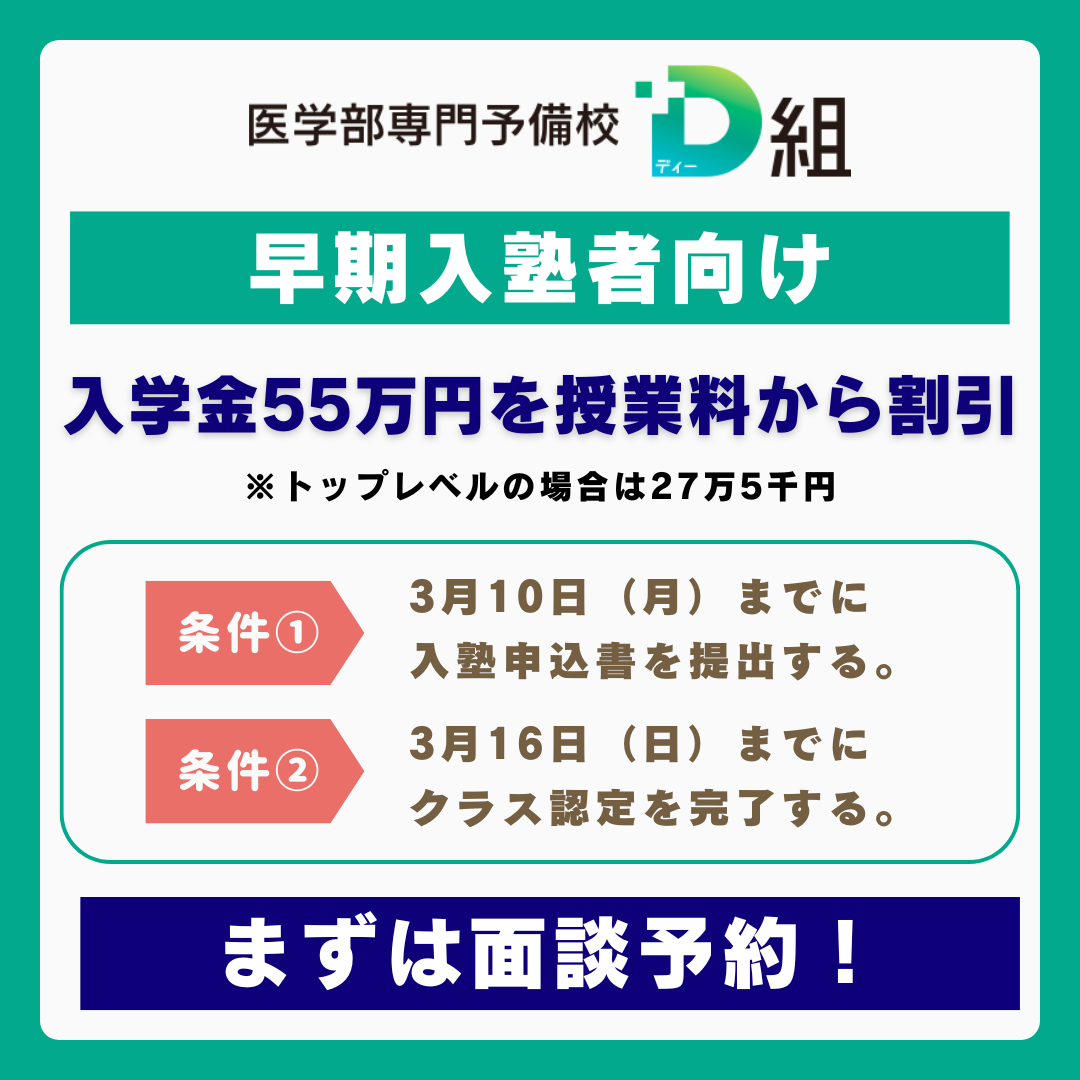獨協医科大学物理(2024年度/一般前期1日目)-入試情報
出題形式
選択肢(100%)
試験時間
理科2科:120分
難度(5段階)
3.2(標準)
分量(必要時間)
62分(標準)
合格に要する正答率予想
73%
大問数
5問
出題内容
第1問:小問集合,
第2問:ドップラー効果の導出と血流計,
第3問:コンデンサーへの導体挿入,
第4問:水槽に沈めたシリンダー,
第5問:台につながれたばね振り子
求められているもの
極めて私大医学部らしい安定感のある出題である。難しい題材には少し誘導が入るが確かな基礎力がなければ解答は難しい。出題分野に大きな偏りはない。概ね典型的な出題である。広い見識を持ったうえで,経験した信頼性のある解法を適切に素早く行使する,といった臨床医に要する能力が問われていると思われる。
獨協医科大学物理(2024年度/一般前期2日目)-入試情報
出題形式
選択肢(100%)
試験時間
理科2科:120分
難度(5段階)
3.1(標準)
分量(必要時間)
65分(やや多い)
合格に要する正答率予想
78%
大問数
5問
出題内容
第1問:小問集合,
第2問:人工衛星軌道,
第3問:相互誘導と変圧器,
第4問:マイケルソン干渉計,
第5問:水素原子のボーア模型
求められているもの
1日目と同様である。
獨協医科大学物理(2024年度/一般後期)-入試情報
出題形式
選択肢(100%)
試験時間
理科2科:120分
難度(5段階)
3.6(やや難しい)
分量(必要時間)
83分(多い)
合格に要する正答率予想
81%
大問数
5問
出題内容
第1問:小問集合,
第2問:剛体のつり合い,
第3問:E×Bドリフト,
第4問:熱サイクル,
第5問:中性子線干渉
求められているもの
高難度で有名な現象の出題に目を引かれるが,全体に比してさほど多くないため,制限時間の厳しさからしても「時間を有効に使い,解きやすい問題を正確に解く試験である」という姿勢で受験することを考えれば,極端に高難度の試験とは言い難い。正確な自己評価のもとに得意分野で高い能力を発揮する学生を求めているのだろう。おそらく臨床医,専門医としての適性を測る試験となっている。
今月は医学部専門予備校D組物理科講師の三宅 唯先生に獨協医科大学物理の入試対策をお聞きしました。
極めて優れた一貫性
三宅 唯先生よろしくお願いいたします。早速ですが近年の獨協医科大学の物理には特別な傾向はありますか。
そうですね。他の私立医学部に比べて特に変わっているなと感じるのは,出題の一貫性です。分量も難度も驚くほど一貫性があります。物理の入試では出題テーマに応じて小問数が異なり,読ませる問題文の量も大きく異なるのが普通なのですが,獨協医科大学に限って言えば異常なほど一貫しています。出題のばらつきを最小限に抑える努力をされているのでしょう。一般前期の1日目と2日目は概ね同じ難度・同じ分量で出題されており,どちらが有利というものはありません。後期はかなり高級な題材が出題されることもありますが,形式としては前期と同じです。
出題は粒ぞろい

獨協医科大学の物理の出題における一貫性とは具体的にはどういったものでしょうか。
2004年までは記述形式で大問3問でしたが,2005年から現在に至るまで,マークシート形式で出題数は大問5問,1大問あたりの小問は4~5問で一貫しています。普通はテーマによって問える事柄が多かったり少なかったりするものですが,大学側からのかなり厳しい出題指示によって,出題者が設問数や読ませる文章量を強い意志で調整しているのだと思います。かなり思い切りの必要な仕事です。出題者は大変だろうなぁと心中お察しいたします。本当に頭が上がらない素晴らしい仕事をされています。私個人的には画一化・システム化が大好きなので,そういった仕事の価値を人一倍理解できると自負しております。尊敬します。そういう個人的な思いもあり,今月の学習アドバイスに獨協医科大学を選びました。
設問数と文章量だけでなく難度もかなり調整されているため,おそらく配点は1大問20点,小問は4点または5点と均一に配分されていると考えられます。これだけの一貫性を出しているのは単純に採点のしやすさを与えるだけでなく,学力測定に平等性を与えるためなのだろうと思います。
驚くべき網羅性
問題量が統一されているだけでは学力測定の平等性は出せないと思いますがいかがでしょうか。
その通りです。獨協医科大学の物理には,さらに出題分野に関しての強い網羅性があるのです。力学,電磁気学,波動,熱力学,原子物理の全範囲からまんべんなく出題されます。特に近年その傾向が強まってきました。2012年までは5つの大問のすべてが「1つの大問につき1つの現象」を出題するテーマ大問でしたが,2013年頃から徐々に第1問で問われる現象が増えはじめ,現在では第1問が完全に小問集合になり,網羅性がさらに向上しました。他の私立医学部でも網羅性を担保するため小問集合を課しているところは昔から多いのですが,その中でもかなりバランスがとれた出題といえます。加えて言えば近年数年分の出題を統計しますと,各分野の出題比は概ね検定教科書の各分野のページ数の比に一致します。一様な学習により一様な成績が現れるわけです。おそらくこれもある程度は計算して出題しているのでしょう。恐れ入ります。
傾向に応じた学習戦略
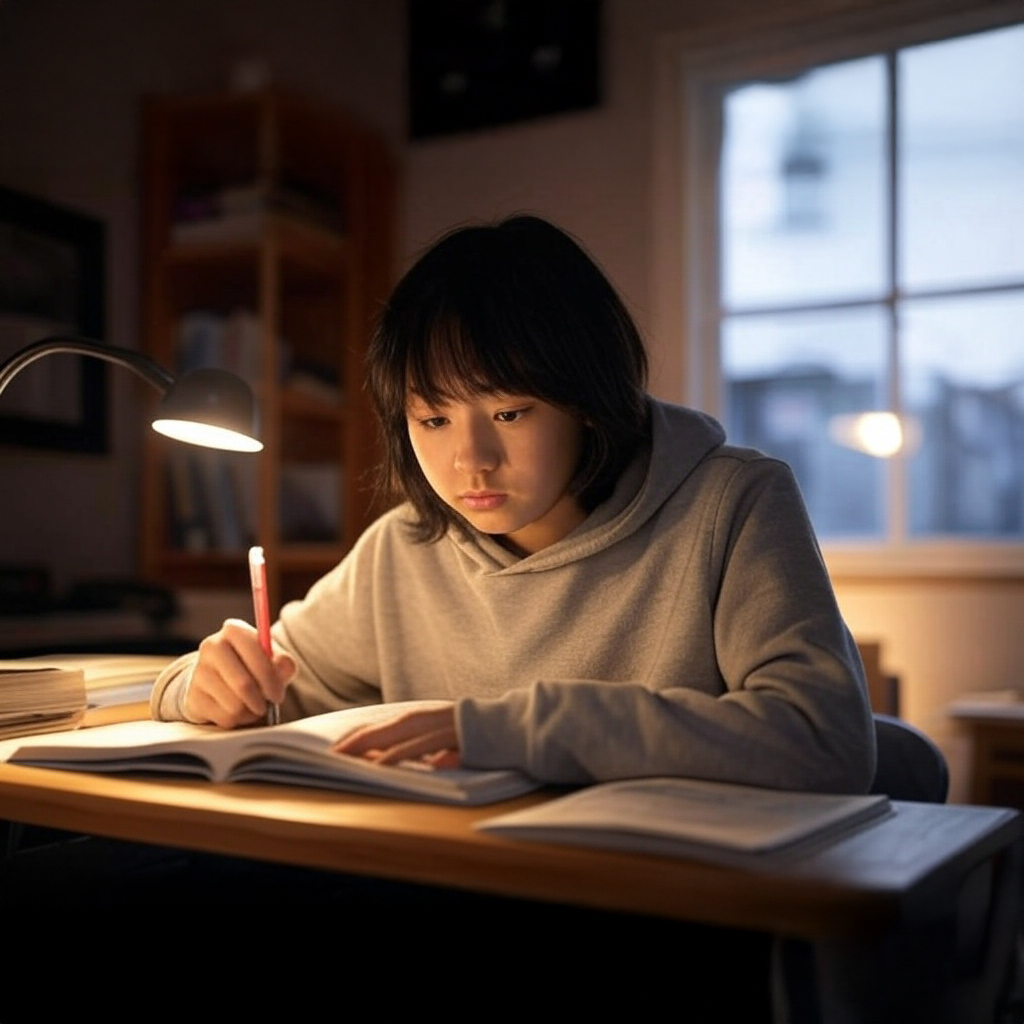
そのような獨協医科大学の出題傾向に対して,「これだ!」という学習戦略はありますか。
うーん,難しい質問です。近年の出題の網羅性により,一層「範囲を絞って勉強する」という戦略の勝ち筋が見えなくなりました。試験時間60分に対する分量としては少し多めの出題なのですが,1大問白紙で出してよいほどの分量ではない。せいぜい1,2小問分,解く時間が足りない程度です。すると,分野に学力の偏りがあると,それが如実に成績差として生じます。物理という一つの教科であっても,誰しも苦手分野と学力の偏りはあるものです。獨協医科大学の合格という目標にあたっては,堅実に苦手を克服していくほかありません。学習は網羅的におこなうべきです。
さらに難度に関して言えば,第2問から第5問のテーマ大問では大抵,最後の小問が難しくなっているため,高得点をとるには深く勉強することも必要です。勝ちにいくことを考えず「負けないように受験する」とか「合格最低点を目標とする」という消極的な観点からすれば,第1問の小問集合と,他の全ての大問において最後の小問を除くすべての小問を8割得点することが必須です。すなわち全体の65%を得点することが真の最低ラインだと思われます。「真の」といったのは、正答率65%で大丈夫ということではないからです。「65%以上取れているのに受からなかった」という理不尽なクレームを避けるため、普通の予備校はもっと高く算定します。いずれにせよ受験生に求められているのは穴のない学習です。理論講義の復習を徹底し,さらに基礎から標準までの問題経験をなるべく多く積みましょう。
分野を絞って学習する戦略は通用せず,浅く広くの学習でいいわけでもない。総じて,獨協医科大学に一発逆転合格するような付け焼刃の学習戦略は存在しないという結論になります。普通に物理をしっかり頑張ってくれとしか言いようがありません。ご期待に沿えず申し訳ございません。
物理で勝負することは可能か
獨協医科大学の物理で勝ちにいきたい受験生へもアドバイスをお願いします。
そうですね。他の教科の成績が芳しくなく「物理で少しでもアドバンテージが取りたい」という受験生もいるはずですからね。大丈夫です。物理の学習に対して積極的であれば勝機があると思います。難度の高い小問,すなわち第2問から第5問のテーマ大問の最終小問が勝負どころです。物理にかけてきた情熱が報われる小問となっています。難しい小問の割合は概ね全体の15%~20%程度です。これは決して小さくない得点です。是非とも物理に時間をかけてみてください。
堅実な人間の形成
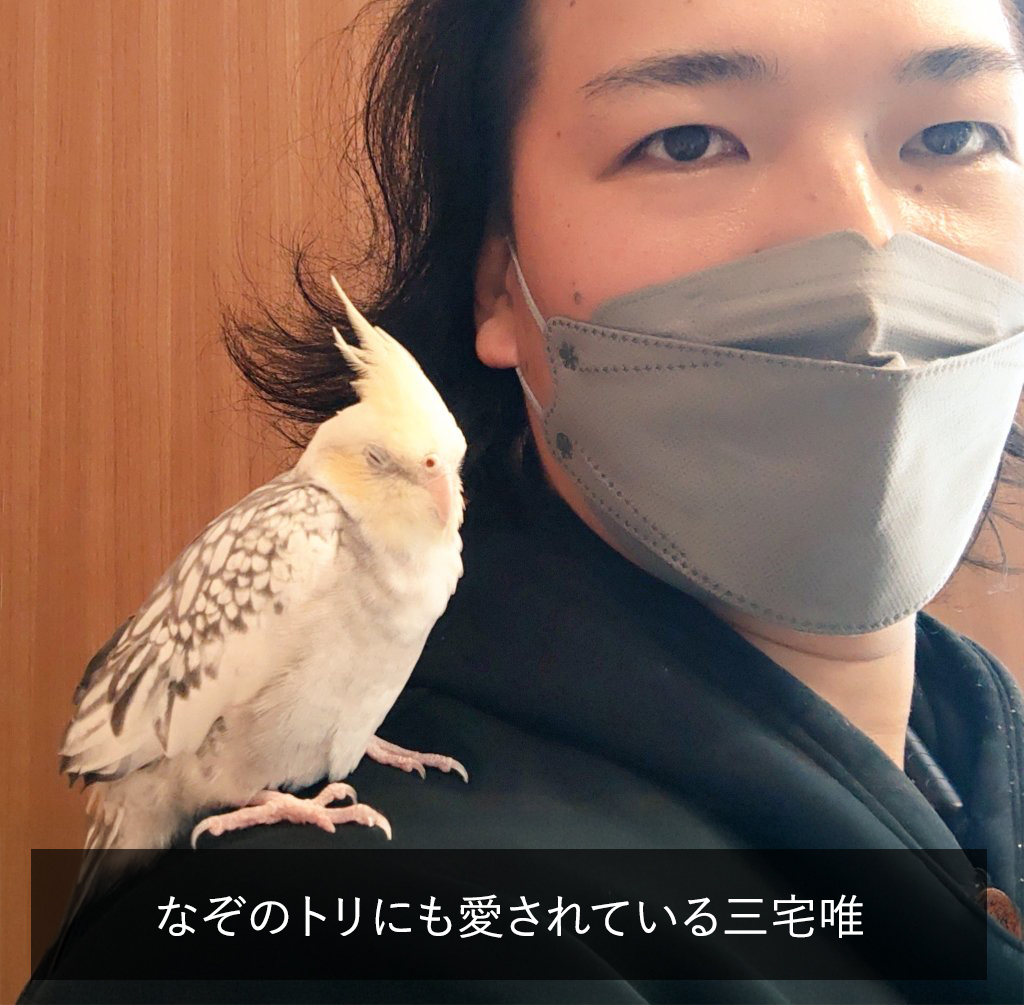
三宅 唯先生としては,獨協医科大学の出題傾向にはどういった大学の意図が現れていると想像されますか。
総じて獨協医科大学の入試は試験としての完成度が高く,物理に時間を費やしてきた受験生の努力が報われる試験です。しかし,その反面,物理が苦手で手を抜いてしまった受験生には容赦ない出題です。受験生の学力差が如実に現れる出題であり,上手く誤魔化して点数を稼ぐことが難しい入試です。すなわち逃げ道がありません。
設問における解法の誘導があまりないのも特徴です。解答に使用する物理法則は自分で選び,自分で文字を置いて自力で計算するという,物理において基本的な能力が問われています。行き当たりばったり,その場で考えれば何とかなるとかそういう問題ではありません。典型問題については試験までによく研究しておき,すべてを用意しておくように努めなければなりません。医師国家試験を通過する資質が問われているのだと思います。来たるべき時のために万全の準備をしておくという,勉強に対する基本的な姿勢です。医療現場で対峙するあらゆる困難を想定し,予め入念な準備をしておくのと同様です。
獨協医科大学の建学の精神は「学問を通じての人間形成」です。準備不足で出たとこ勝負の私のような怠惰な人間に寛容であるとは到底思えません。私のことはほっといて,皆さんは医師となるにあたって日々相応しくあろうと努めてください。
ドリフトしていくのも人生
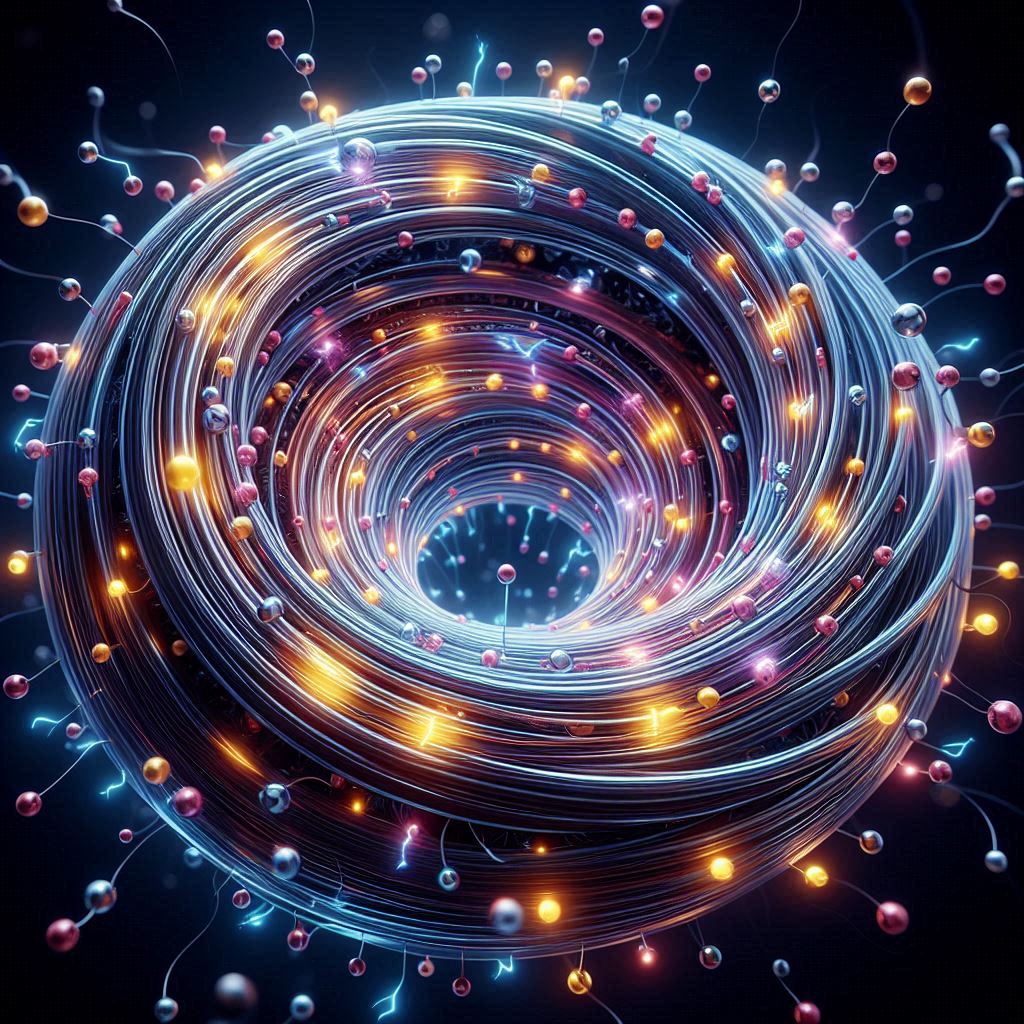
新学期を迎え受験勉強を本格的に始める受験生に熱いメッセージをお願いします。
物理の学習においては「1を聞いて10を知る」はおろか,「10を聞いて1を知る」ことすら難しいものです。3~5ぐらいわかった気がしたらとりあえず先に進んでみてください。同じものを見ても2周目には少し高い視点で見ることができます。周回するごとに高い視点となります。一様磁場中の荷電粒子の等速螺旋運動を想像してください。そうです。何かわからないけどそういう感じです。むやみに電場を加えるのはやめてください。余計な方向にドリフトしていきます。でもドリフトしていくのも人生です。広い視点でものを見ることができるのも実に素晴らしいことです。無駄なことなど何一つありません。毎日は発見にあふれています。世界はあなたが見つけてくれるのを待っています。人生に科学の視点を。
ちなみに獨協医科大学では2024年後期第3問で「電磁場による荷電粒子のドリフト運動」が出題されています。難問として有名な問題ですね。是非ともチャレンジしてみてください。
最高の曲とは
最後に三宅 唯先生の好きな音楽を教えてください。
私が一番好きなのは私が作った曲です。どれも素晴らしい曲ばかりですが残念ながらもう披露する機会はありません。実に残念なことです。やっほう。
なるほど,三宅 唯先生ありがとうございました。引き続きD組の医学部受験生たちにも熱意あるご指導をよろしくお願いいたします。
医学部専門予備校D組では、現在の成績に関係なく、12人以内の少人数クラスでこのような専門性の高い優秀な講師の対面講義を受けることができます。少人数制だからこそ可能な、きめ細やかな指導と、質疑応答の時間を豊富に設けることで、生徒一人ひとりの理解度を深め、着実に実力アップを目指します。さらに、アットホームな雰囲気の中で、周りの生徒と切磋琢磨しながら学ぶことができるのもD組の魅力です。